フェルデンクライスの指導者で教育についてたくさんの研究をしてきたキャロルさんという方がある本を書いています。
興味深かったのでその内容について書きたいと思います。
「マインドセット(信念、思い込み)」という、英語の本です。
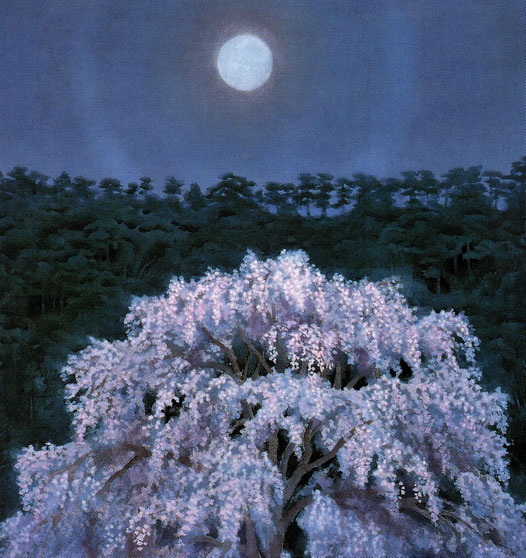
彼女はある子供の成績、芸事などが他の子供より非常に優れていることについて研究しました。
私たちは、「もともと」素晴らしい才能がある人がいるという考え方を持って生きています。
しかし実験の結果、いわゆる優れている子供というのは、その子のIQとは関係がないということがわかったのです。
では何が違うのか。
それは「学びに対する態度」でした。
私たちは、「知性というものは固定されている」という考えがあります。
だから私の子供のように「知的障がいがある」「発達障がいがある」と診断されると悲観したり、そんなはずはないと怒り始める親御さんがいたりするのです。
変化しないと考えているからです。
世間も同じ考え方を持っています。
その思い込みが浸透しているために、親から「あなた頭賢いわね」と言われた子供というのは、自分が賢くないというような状況を見せてしまうことを恐れていると彼女は言っています。
自分が間違いを起こしてしまうような状況というのを非常に恐れていると。
これは子供より大人の方が多いような気がしますが、子供がそのまま育ったら大人なので自然の流れですね。
これが、固定されたマインドセット(信念、思い込み)だと彼女が呼んでいます。
子供によっては自分が工夫をどれだけするか、どれだけそこに時間を費やすかということによって、もっと伸びていくことができる、という考えを持っている場合もあります。
自分の行動によって、今の状態は変わっていくんだと。
だから今の自分の状態は、学ぶ「方法」によって変えていくことができるものだというふうに思っています。
これは「成長していくマインドセット」だと彼女は言っています。
ですので、自分の知性というのが決まっていてそこにいるのではなくて、どのように行動するか、というところでもっと遊びなさいと述べています。
子供に対する声がけでは、『子供の「知性」を褒めるのではなく、「行動」を褒めなさい』と言います。
例えば「ピアノ上手だね」と言うのではなくて
「練習して偉かったね」「発表会に出てすごかったね」「部分的に練習して偉かったね」など、行動を賞賛する声がけが良いと言っています。
行動を褒めていくことによって、子供はより成功していく方向に向かっていくことができます。
でも、簡単に言っていますがこれを実際にするのはそんなに簡単ではありません。私もできていません。できる時とできない時と。。。
でも少なくとも、フェルデンクライスメソッドを体験すると、変化はいつでも起きるということを実感でき、できないと思っていたことができるようになるという経験を得ることができます。
だから確信を持てるのは、これは理解できないとか、どうやってやったらいいのかわからない、ではなくて、「まだ」できるようにはなっていないと。
楽譜が読めないとするならば、「まだ」読めない。
それでかなり違う感じがしますよね。
自分で十分にできないというふうに思っていることというのは、それまでの人生経験において、そこに繋がる何かが起こっているからです。
私が小学2年の頃、お料理を母としていました。
そこで母がイライラしていたようで「要領の悪い子ね!」と言ったのです。
私は料理は嫌いではありませんでしたが、するのが嫌になってしまいました。
そして自分は要領が悪いのだと感じて、ことあるごとに友達などに言っていました。
要領よく立ち回らなければならない場所は避けたりしていました。
そして、社会人になって事務の仕事をしていた時上司に
「仕事早い!もう終わったの?間違いもないし要領がいいんだね」
と言われびっくりしたのです。
そこで私はようやく、あれは母が言った不適切な言葉だったんだと理解できました。
確かに要領悪い小学2年生だったかもしれませんが、変わりますからね。
あれはできない、これはできない、でもそれは『まだ』できていない、それだけなのです。
ピアノでこの動きができないんだよな〜『まだ』。
算数でこういう問題が出てくるとわからなくなるんだよな〜『まだ』。
私は今まで10人くらいのピアノの先生に着いた経験から、才能がある人というのは、先生としては最悪だと思っています。
なぜならそういう人は苦労しないわけです、出来ちゃうものだから。
だからそれについて分解して考えていくことができません。
当然、できなくて困っている生徒さんと自分を関連づけて考えることなどできません。
だから才能のある先生が育てられるのは、才能のある生徒だけです。
でも才能のある生徒というのは、自分で考えることができるのでそもそもそれほど指導を必要としていないことが多いです。
始めたときはあまりできないような人でも、十分に注意を向けて、学ぶことを学ぶということを考えながらやっていけば、必ず進歩していくことができます。
でも、変化を起こす、成長する、ということには『何かをする』ということは必ず含まれています。
やらないうちから「できない」と言っているのは違いますね。
まず初めに、一体どこに対して自分が「固定化されたマインドセット」を持っていて、どこが「成長するマインドセット」なのかということを識別することが必要です。
そうすることで、「成長するマインドセット」を使えるようになり、常に成長し続けることができるようになります。
自分ができるようになれば、それを子供にも伝えていくことができます。
おすすめ動画
私の中では誰もが知っている逸話だと思っていたのですが、時代を経る
ごとに知らない人も多くなってきたようなので改めて。
世界的な大バイオリニスト、五嶋みどりさんの演奏です。
タングルウッドの奇跡と呼ばれ、アメリカの教科書にも載っているこの演奏。
本番演奏中にバイオリンの弦が2回も切れるのに、全く動じず最後まで弾ききった彼女の演奏に、指揮者のバーンスタイン氏が感動して涙を拭っているのが印象的です。
私はみどりさんの演奏が大好きなので、CDも色々持っていたしYouTubeも見ていて、インタビューなどもたくさん聴きました。
上のブログに当てはめればまさに「成長するマインドセット」の人だなと思いました。
私たちは彼女と同じになれるとは言いませんが、近づくことはできます。
できることが重要なのではなく、近づこうとすること、近づくために行動することが大切です。

コメントをお書きください